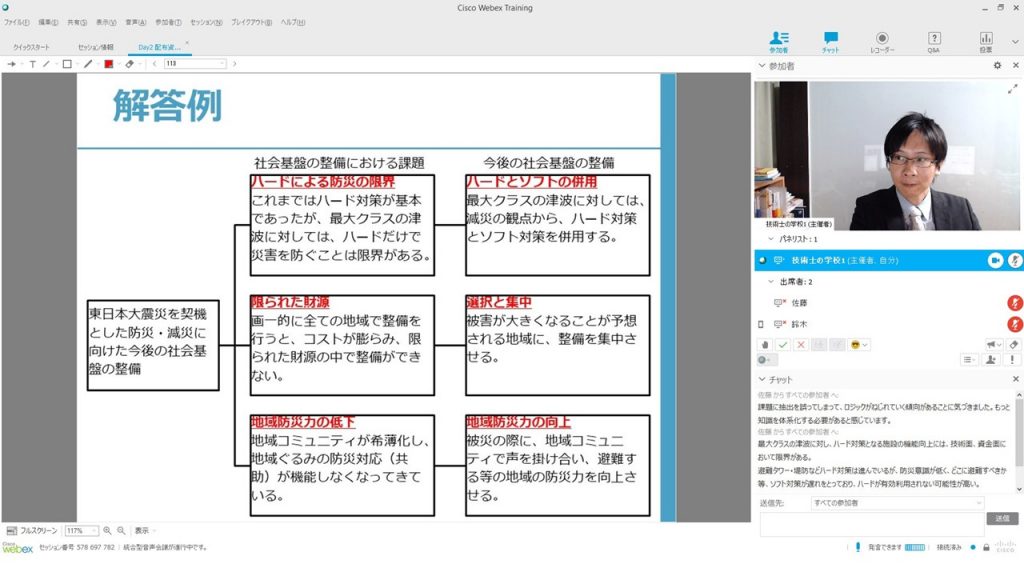2023.05.29
- コラム
【技術士二次試験完全ガイド】試験内容や過去問、突破法を解説

「活躍する先輩の姿を見て、技術士の第二次試験にチャレンジしようと思う!第一次試験とは違うと聞くけれど、第二次試験はどのような試験なの?」
「社内で技術士資格を推進しているので、少しでも早く第二次試験に合格したい…」
テスト
第一次試験を終えて実務経験を積みいざ第二次試験にチャレンジできる時期になったものの、改めて「第二次試験とはどのような試験なのか」詳しく知り合格を目指したい方は多いのではないでしょうか。
技術士の第二次試験は、技術士になるために修習技術者が受けられる国家試験です。
多くの方が受験した第一次試験とは異なり、筆記試験と口頭試験の2段階に分かれています。平均合格率が16.8%と低く独学で闇雲に勉強しても、合格が難しい試験です。
 ※修習技術者とは第一次試験合格者や指定の教育課程修了者が持つ資格
※修習技術者とは第一次試験合格者や指定の教育課程修了者が持つ資格
第二次試験は確かに難しい試験ではありますが、晴れて技術士として活躍されている先輩たちからは「取得してよかった」という声が多いです。

ただし、技術士第二次試験は合格までに、平均10回受験すると言われています(建設部門・筆記試験の場合)。
 ※建設部門・筆記試験の場合
※建設部門・筆記試験の場合
第二次試験のチャレンジを迷っていると技術士として活躍できる時期を遠のいてしまうので、いち早く第二次試験合格を目指すことが重要です。
そこでこの記事では、技術士第二次試験の概要や合格率、日程や、出題される問題など、第二次試験の基礎知識を分かりやすく解説しています。
最後まで読めばどのような試験なのか理解でき、何から勉強すればいいのか分かります。
少しでも早く本格的に勉強を始めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。
目次 [非表示]
目次 [表示]
1.技術士第二次試験の概要

まずは、技術士第二次試験を検討するうえで知っておきたい概要をまとめてご紹介します。
そもそも受験資格があるのか、どのように受験するのかなど、試験勉強に取り組む前に気になる情報ばかりなので、ぜひ参考にしてみてください。
| 技術士第二次試験の概要 |
|---|
|
・第二次試験の受験資格は?:技術士第二次試験の受験資格 ・合格の基準は?:技術士第二次試験の合格基準 ・第二次試験の合格率は?:技術士第二次試験の平均合格率は16.8%(2023年度時点) ・第二次試験の日程は?:技術士第二次試験の日程(2024年時点) ・受験する手順は?:技術士第二次試験の流れ |
1-1.技術士第二次試験の受験資格

技術士第二次試験を受験するには、技術士の第一次試験合格もしくはJABBEの認定プログラムを修了して「修習技術者」になる必要があります。
そのうえで、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
| 勤務体系 | 第二次試験受験の条件 |
|---|---|
| 技術士補として勤務している場合 |
ケース1 技術士補として通算4〜7年以上の実務経験がある ・ 総合技術監理部門を除く技術部門:4年以上 ・ 総合技術監理部門:7年以上 |
| 上記以外の場合 |
ケース2 職務上の監督の下で通算4〜7年以上の実務経験がある ・総合技術監理部門を除く技術部門:4年以上 ・ 総合技術監理部門:7年以上 |
|
ケース3 技術資格に関する実務経験が7〜10年以上ある ・総合技術監理部門を除く技術部門:7年以上 ・ 総合技術監理部門:10年以上 |
参考:文部科学省「令和6年度技術士第二次試験の実施について」
参考:一般社団法人 日本技術者教育認定機構「技術士への道」
※上記以外の業務では科学技術(人文科学のみに関わる業務を除く)に関する専門的応用能力を必要とする業務が対象(単純な技能的な業務、研究・設計等に付随する庶務的な業務を除く)
※ケース1とケース2の期間を合算することが可能
技術士補として通算4年以上(総合技術監理部門の場合は7年以上)の実務経験があると、第二次試験の対象です。
また、修習技術者になる前から専門的応用能力を必要とする業務に携わっていた場合は、その期間を含めて7年以上(総合技術監理部門の場合は10年以上)の実務経験があれば受験対象になります。
【技術士の第二次試験の対象者となる例】
・技術士補として勤務していた経験が通算で4年以上ある
・〇〇分野の業務に4年間従事して、その後知識を活かして〇〇の仕事に4年間従事
※基本的には技術士法に記載されている業務に従事していれば職務経歴になりますが、受験資格に該当するのか判断が難しい場合は、公益社団法人日本技術士会に問い合わせをして確認してください。
技術士試験では業務経歴書などを提出して、業務経歴や業務内容の詳細を確認します。
条件を満たせないと受験資格がないと判断されるため、今までの実績や職歴をまとめて受験資格があるか確認してみましょう。
【理系の大学院に通学した場合は最大2年の実務期間を短縮できる】
学校教育法による大学院修士課程・博士課程を修了した場合(国内の大学院・理系系統の場合のみ)、どのパターンにおいても2年を上限に実務経験を短縮できます。
学部学科と技術士試験の関連性の判断が難しい場合は、公益社団法人日本技術士会に問い合わせをして確認してください。
1-2.技術士第二次試験の合格基準
技術士試験の合格基準は、指定範囲ごとに全得点の60%以上の得点を取得することです。
指定範囲とは、どの範囲の科目で60%以上の得点が必要なのか定めているものです。
具体的には、下記のように決められています。
| 技術部門の項目 | 合否基準 | 点数・詳細 |
|---|---|---|
| 必須科目Ⅰ | 60%以上 (24点以上) |
記述式(600文字×3枚) 40点満点 |
| 選択科目Ⅱ | 60%以上 (36点以上) |
記述式(600文字×3枚) 30点満点 |
| 選択科目Ⅲ | 記述式(600文字×2枚) 30点満点 |
|
| 総合技術監理部門の科目 | 合否基準 | 点数・詳細 |
| 必須科目 | 60%以上 (60点以上) |
択一式(40問出題) 50点満点 |
| 記述式(600字×5枚以内) 50点満点 |
||
| 選択科目 | 60%以上 (24点以上) |
記述式(600文字×3枚) 40点満点 |
| 60%以上 (36点以上) |
記述式(600文字×3枚) 30点満点 |
|
| 記述式(600文字×2枚) 30点満点 |
例えば、技術部門の筆記試験では、必須科目と選択科目双方で60%以上の得点が合格ラインです。
選択科目Ⅱと選択科目Ⅲは双方を足して60%以上になればいいので、選択科目Ⅱが23点、選択科目Ⅲが13点であっても問題ありません。
また口頭試験は、下記のように質問事項ごとに60%以上の得点が必要です。
| 項目 | 合否基準 | 点数・詳細 |
|---|---|---|
| 技術士としての実務能力 | ||
| 60%以上 (18点以上) |
コミュニケーション、リーダーシップ 30点満点 |
|
| 60%以上 (18点以上) |
評価、マネジメント 30点満点 |
|
| 技術士としての適格性 | 60%以上 (12点以上) |
技術者倫理 20点満点 |
| 60%以上 (12点以上) |
継続研さん 20点満点 |
評価は採点者がマニュアルに沿って行っていますが、採点項目や詳しい基準は非公開となっています。
【技術士試験の評価基準】
技術士試験の合否通知書では、A・B・Cの3段階で評価されます。
・A評価:60%以上
・B評価:40~59%
・C評価:39%以下
指定範囲ごとに60%以上を獲得できているかどうかが基準になります。
1-3.技術士第二次試験の平均合格率は16.8%(2023年度時点)
技術士第二次試験の平均合格率は、16.8%(1958年~2023年度までの平均合格率)です。
 参考:公益社団法人日本技術士会「技術士第二次試験結果一覧表」
参考:公益社団法人日本技術士会「技術士第二次試験結果一覧表」
2023年度の第二次試験合格率は11.8%で、直近5年の第二次試験も11%台をキープしている状況です。
 参考:公益社団法人日本技術士会「技術士第二次試験結果一覧表」
参考:公益社団法人日本技術士会「技術士第二次試験結果一覧表」
約10人に1人しか合格できないと考えると、第二次試験の合格率は低いと言えるでしょう。
第二次試験は難易度が高く、平均受験回数が10回(建設部門・筆記試験の場合)だと言われています。
 ※建設部門の筆記試験の場合
※建設部門の筆記試験の場合
第二次試験に必要な実務経験を積んでから試験勉強を開始すると、合格までに10年以上かかることも想定されます。
そのため、第二次試験合格を目指すと決めた段階から、計画的に勉強を進めることが欠かせません。
▼技術士試験の合格率については、下記の記事でも詳しく解説しています。
「技術士 合格率」
1-4.技術士第二次試験の日程(2025年)

技術士第二次試験は、申し込みから合格発表までを含めて約1年かけて実施 します。
2025年度の第二次試験の日程は、下記のとおりです。
| 日にち | 試験対象 | 期日 |
|---|---|---|
| 受験申し込み受付 例年4月上旬~中旬 |
‐ | ・郵送受付:令和7年4月1日(火)~4月16日(水) ※4月16日消印有効 ・WEB受付:令和7年4月1日(火)9:00~4月15日(火)17:00 |
| 筆記試験 例年7月中旬 |
・総合技術監理部門の必須科目 | 令和7年7月20日(日) |
| ・総合技術監理部門を除く技術部門 ・総合技術監理部門の選択科目 |
令和7年7月21日(月・祝) | |
| 筆記試験合発表 例年10月下旬 |
・筆記試験受験者 | 令和7年11月4日(火)予定 |
| 口頭試験 例年12月上旬~1月 |
・筆記試験合格者 | 令和7年12月上旬~令和8年1月中旬 |
| 合格発表 例年3月上旬 |
‐ | 令和8年3月13日(金)予定 |
参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験 実施案内」
技術士第二次試験の最新日程は、公益社団法人日本技術士会の公式サイトで公表されるので、定期的に確認するようにしましょう。
とくに、注意したいのは、第二次試験の受験申し込み受付期間です。
例年4月上旬~中旬にかけて申し込み受付をするのですが、この期間を過ぎた申請は受け付けていません。
次の章でも触れますが事前に揃える書類があるため、申し込み受付期間を把握して準備をするようにしましょう。
1-5.技術士第二次試験の流れ

技術士第二次試験は、必要な書類を送付し受験資格を得たうえで、筆記試験、口頭試験の順に受験します。
ここでは、技術士第二次試験の流れを簡単に紹介するので、技術士合格までにするべきことを理解するためにも参考にしてみてください。
| 第二次試験の試験内容が気になる方は下記からご覧ください |
|---|
|
第二次試験の試験内容からチェックしたい場合は、下記のリンクをクリックして該当のページからご覧ください。 ・技術部門の筆記試験:【技術部門・筆記試験】必須科目・選択科目 ・総合技術監理部門の筆記試験:【筆記試験・筆記試験】総合技術監理部門 ・技術監理部門と総合技術監理部門の口頭試験:口頭試験 |
ステップ1:第二次試験の申し込みに必要な書類・費用を揃える
まずは、技術士の第二次試験に必要な下記の書類を用意します。
| 全員が必要な書類 |
・受験申込書 ・実務経験証明書 ・証明写真 ・受験手数料払込受付証明書 ・技術士補となる資格があることを証明する書類 |
| ケースに応じて 必要な書類 |
・監督下での経験を受験資格にする場合: ・大学院での研究期間を受験資格にする場合: ・試験の一部免除を受ける場合: |
参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験 受験申込み案内」
※上記は主な書類です。受験資格により必要な書類が異なるので申し込み案内を確認してください
受験申込書と実務経験証明書、受験料の振込用紙などは、配布期間中に公益社団法人日本技術士会のウェブサイトからダウンロードする、もしくは公益社団法人日本技術士会から申込冊子を取り寄せます。
また、技術士第二次試験の受験料は先払いで、申込時に受験手数料払込受付証明書を添付しなければなりません。
受験料は1技術部門につき14,000円(税抜)なので、申込期間内に金融機関や郵便局で支払いを済ませましょう。
| 【総合技術監理部門と技術部門を併願する場合】
総合技術監理部門と技術部門を併願する場合は、2部門分同時に受験申込書を提出します。2部門分の28,000円(税抜)の事前申し込みが必要です。 |
ステップ2:期日内に申し込みをする
ステップ3:筆記試験を受ける
受験資格を獲得できたら、指定の期日に筆記試験を受けます。
筆記試験は全国12か所(2024年時点)で開催しますが、詳しい会場は手持ちの書類で確認してください。
| 【筆記試験の会場】
北海道、宮城県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、沖縄県 |
参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験 実施案内」
また、筆記試験時の持ち物は細かく指定されているため、試験に適合しているか事前に確認しておきましょう。
|
【筆記試験の持ち物】 ・受験票 ・HB以上の濃さの鉛筆またはシャープペンシル ・消しゴム ・手動の鉛筆削り ・透明な直定規(長さ30cm程度まで) ・通信機能や電卓機能のない時計 ・電卓(四則演算、数値メモリのみの電卓) ・写真付きの身分証明書(運転免許証、社員証など) |
参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度 技術士第二次試験受験申込み案内」
※2024年時点の持ち物です
筆記試験の合否は、合格発表日に公益社団法人日本技術士会もしくは文部科学省のホームページに合格者の受験番号が掲載されます。
筆記試験に合格した場合、口頭試験の日程と場所が後日郵送で届きます。
ステップ4:合格者のみ口頭試験を受ける
筆記試験の合格者は、口頭試験を受けます。
口頭試験の場所(東京都)の詳細や日時は個別に通知されるため、指示に従ってください。口頭試験も筆記試験同様に、合否発表日に公益社団法人日本技術士会もしくは文部科学省のホームページに合格者の受験番号が掲載されます。
合格した場合は、後日郵送で「技術士第二次試験合格証」が届きます。
ステップ5:技術士の登録をする
技術士第二次試験に合格し「技術士第二次試験合格証」を受け取っただけでは、技術士として名乗ることができません。
技術士と名乗り活躍するには、技術士登録が必要です。公益社団法人日本技術士会が定めている技術士登録簿の登録手続きを行い完了すると、技術士と名乗って活躍できるようになります。
このように、技術士第二次試験は1年をかけて段階的に取り組むことがあるため、全体的な流れを把握して計画的に進めましょう。
2.技術士第二次試験の試験内容

技術士第二次試験の概要が理解できたところで、詳しい試験内容をご紹介します。
第二次試験は「技術部門」と「総合技術監理部門」で、試験内容が異なります。
| 部門 | 試験科目 |
| 【技術部門・筆記試験】必須科目・選択科目 | 必須科目Ⅰ・選択科目Ⅱ・選択科目Ⅲ |
| 【筆記試験・筆記試験】総合技術監理部門 | 必須科目・選択科目Ⅰ・選択科目Ⅱ・選択科目Ⅲ |
| 【口頭試験】技術部門・総合技術監理部門の筆記試験に合格した場合のみ口頭試験 |
技術部門:技術士としての実務能力・技術士としての適格性
総合技術監理部門:「総合技術監理部門」の必須科目に関する技術士として必要な専門知識や応用能力・技術士としての実務能力・技術士としての適格性
|
あなたが受験する部門ではどのような試験を受けるのか、大まかな内容を把握しておきましょう。
2-1.【技術部門・筆記試験】必須科目・選択科目
技術部門の筆記試験は、建設や下水道、農業などの専門的な分野の知識や技術士としての資質を問う筆記試験です。
必須科目と選択科目のどちらも満点の60%以上を獲得すると合格になります。
| 科目 | 時間・点数 | 概要 |
|
|
2時間 60%以上 (40点満点) |
記述式(600文字×3枚) 技術部門ごとの基礎知識を使い問題解決方法を提示する |
|
選択科目Ⅱ |
3時間30分 60%以上 (各30点満点) |
記述式(600文字×3枚) 専門科目の基礎知識と応用力を確認する |
|
選択科目Ⅲ |
記述式(600文字×2枚) 専門科目の問題解決能力、課題遂行能力を確認する |
2-1-1.必須科目
必須科目は、現代社会が抱える問題について基礎知識を用いて解決、遂行するための問題が出題されます。
記述式なので部門ごとの業界の動向や最新の資料を理解したうえで、的確に課題を捉えて解決策などを600文字用の答案3枚以内にまとめます。
|
必須科目 |
|
|
出題内容 |
現代社会が抱える問題について基礎知識を使って解決方法を提示し、遂行する提案を問う |
|
評価 |
技術士に求められる資質能力のうち専門的学識、問題解決、評価、技術者倫理、コミュニケーションについて評価する |
参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験受験申込み案内 」
※技術士に求められる資質能力とは技術士制度で定められている技術士に最低限必要な資質のことです
例えば、建設部門の場合は、官公庁が重要だと考える下記のようなテーマに対して出題される傾向があります。
|
【建設部門のテーマ例】 ・建設分野の発展(人手不足や生産性向上など) ・防災・減災 ・社会資本の維持管理 ・環境問題 |
※選択した部門によりテーマは異なります
幅広いキーワードが対象となるため、各部門と関連性のあるキーワードへの理解、最新の動向を把握しておく必要があるでしょう。
2-1-2.選択科目
選択科目は、選択した科目に関する知識や応用力を問う問題が出題されます。
選択科目は下記の全69科目があり、今までの経験や保有している知識、携わっている仕事などを踏まえて選択します。
例えば、必須科目「農業部門」の場合は、選択科目で「畜産」や「農業農村工学」などの科目を選択することが可能です。
|
部門 |
選択科目 |
|
機械部門 |
・機械設計 ・材料強度・信頼性 ・機構ダイナミクス・制御 ・熱・動力エネルギー機器 ・流体機器 ・加工・生産システム・産業機械 |
|
船舶・海洋部門 |
・船舶・海洋 |
|
航空・宇宙部門 |
・航空宇宙システム |
|
電気電子部門 |
・電力・エネルギーシステム ・電気応用 ・電子応用 ・情報通信 ・電気設備 |
|
化学部門 |
・無機化学及びセラミックス ・有機化学及び燃料 ・高分子化学 ・化学プロセス |
|
繊維部門 |
・紡糸・加工糸及び紡績・製布 ・繊維加工及び二次製品 |
|
金属部門 |
・金属材料・生産システム ・表面技術 ・金属加工 |
|
資源工学部門 |
・資源の開発及び生産 ・資源循環及び環境浄化 |
|
建設部門 |
・土質及び基礎 ・鋼構造及びコンクリート ・都市及び地方計画 ・河川、砂防及び海岸・海洋 ・港湾及び空港 ・電力土木 ・道路 ・鉄道 ・トンネル ・施工計画、施工設備及び積算 ・建設環境 |
|
上下水道部門 |
・上水道及び工業用水道 ・下水道 |
|
衛生工学部門 |
・水質管理 ・廃棄物・資源循環 ・建築物環境衛生管理 |
|
農業部門 |
・畜産 ・農業・食品 ・農業農村工学 ・農村地域・資源計画 ・植物保護 |
|
森林部門 |
・林業・林産 ・森林土木 ・森林環境 |
|
水産部門 |
・水産資源及び水域環境 ・水産食品及び流通 ・水産土木 |
|
経営工学部門 |
・生産・物流マネジメント ・サービスマネジメント |
|
情報工学部門 |
・コンピュータ工学 ・ソフトウェア工学 ・情報システム ・情報基盤 |
|
応用理学部門 |
・物理及び化学 ・地球物理及び地球化学 ・地質 |
|
生物工学部門 |
・生物機能工学 ・生物プロセス工学 |
|
環境部門 |
・環境保全計画 ・環境測定 ・自然環境保全 ・環境影響評価 |
|
原子力・ 放射線部門 |
・原子炉システム・施設 ・核燃料サイクル及び放射性廃棄物の処理・処分 ・放射線防護及び利用 |
参考:公益社団法人日本技術士会「第二次試験 技術部門/選択科目」
※総合技術監理部門の選択科目も上記20部門同様の科目から選択します
選択科目の筆記試験は下記の2段階に分かれており、試験の目的や評価方法などが異なります。
|
選択科目Ⅱ |
目的 |
選択科目の専門的な知識と応用力の確認 |
|
問題内容 |
・選択科目の重要なキーワードや新技術などの専門知識を確認する(Ⅱ-1) ・選択科目に関連する業務の与えられた条件に合わせて、専門知識や実務経験に基づき業務遂行手順が説明でき、業務上で留意すべき点や工夫を要する点などを認識しているか確認する(Ⅱ-2) |
|
|
評価 |
技術士に求められる資質能力のうち専門的学識、マネジメント、リーダーシップ、コミュニケーションの項目を評価(Ⅱ-1とⅡ-2の評価基準を併せて記載) |
|
|
選択科目Ⅲ |
目的 |
選択科目の問題解決能力、課題遂行能力の確認 |
|
問題内容 |
社会的なニーズや技術の進歩に伴う専門的な問題を対象に課題の抽出、分析を行い、問題解決手法、遂行方策を提示できるか確認する |
|
|
評価 |
技術士に求められる資質能力のうち専門的学識、問題解決、評価、コミュニケーションの項目を評価 |
参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験受験申込み案内 」
必須科目との違いは、専門科目ならではのスキルや知識を取り入れて論文を構成する点です。
例えば、建設部門の必須科目では、建設部門すべてに共通するスキルや知識で意見をまとめればよいのですが、選択科目では選択した科目の選択的な知識や最新の動向などを踏まえた論理構成が求められます。
|
【選択科目は科目選びが重要】 技術部門の選択科目は、69もの科目から自身の知識や実績、今後のキャリアを踏まえたうえで適切な選択科目を選ぶようにしましょう。 |
2-2.【総合技術監理部門・筆記試験】必須科目・選択科目
総合技術監理部門は、技術士の部門の中で最上位に位置する部門です。
総合技術監理部門では、継続的な科学技術の発展を目指して、総合的な管理活動ができる人材育成を目的に設置されています。
技術部門より受験条件が厳しく設けられているのも、総合技術監理部門がより高い技術やスキルを求めているためです。
保有しているとステータスになるため、他の技術士資格取得者が挑戦するケースも多いです。
科目内容は技術部門より多く、下記のような科目を受験します。
|
科目 |
時間・点数 |
概要 |
|
必須科目 |
択一式:2時間 記述式:3時間30分 60%以上 (各50点満点) |
択一式(40問出題) 総合技術監理に必要な基礎知識を確認する |
|
記述式(600字×5枚以内) 最新のテーマを踏まえながら総合技術監理に必要な応用力を確認する |
||
|
選択科目Ⅰ |
2時間 60%以上 (40点満点) |
記述式(600文字×3枚) 技術部門ごとの基礎知識を使い問題解決方法を提示する |
|
選択科目Ⅱ |
3時間30分 60%以上 (各30点満点) |
記述式(600文字×3枚) 専門科目の基礎知識と応用力を確認する ※Ⅱ-1:600文字×1枚・Ⅱ-2:600文字×2枚 |
|
選択科目Ⅲ |
記述式(600文字×2枚) 専門科目の問題解決能力、課題遂行能力を確認する |
ここでは、総合技術監理部門の筆記試験の試験科目について、詳しくご紹介します。
技術監理部門の筆記試験とはどこが違うのか、チェックしてみてください。
2-2-1.必須科目
総合技術監理部門の必須科目は、総合技術監理に必要な5つの管理技術を中心に、課題解決能力や応用能力に関する問題が出題されます。
|
5つの管理技術 |
|
|
安全管理 |
安全に関するリスクマネジメントや労働安全衛生管理など |
|
社会環境との調和 |
環境問題や地域環境問題,環境保全の基本原則など |
|
経済性 |
原価管理や品質管理、工程管理、現場の改善など |
|
情報管理 |
知的財産権の保護と活用、情報セキュリティなど |
|
人的資源管理 |
労務管理や人材開発、組織管理など |
総合技術監理部門の出題形式は、択一式と記述式に分かれています。
択一式では財務諸表や在庫管理、労務管理など5つの管理技術に関する基礎知識を確認する問題が中心です。
記述式では下記のような様々なテーマを通じて、総合技術監理部門に必要な応用力を確認します。
|
【過去5年の記述式のテーマ】 2024年度:カーボンニュートラルに関する取り組み状況 |
2-2-2.選択科目
総合技術監理部門の選択科目は、技術部門の必須科目+選択科目と同等の試験内容です。
|
科目 |
目的 |
概要 |
|
選択科目I |
技術部門に共通する知識や応用力の確認 |
技術部門ごとに必要な専門知識や応用能力などに関する問題 |
|
選択科目Ⅱ |
選択科目の専門的な知識の確認 |
選択科目についての専門知識、応用能力に関する問題 |
|
選択科目Ⅲ |
選択科目でのマネジメント能力の確認 |
選択科目についての問題解決能力、課題遂行能力に関する問題 |
そのため、総合技術監理部門と技術部門を併願することも可能です(選択科目が対応する場合のみ)。このときに選択科目が対応していないと併願できないため、注意してください。

また、併願の場合は両部門の筆記試験に合格しないと、口頭試験に進めません。
例えば、技術部門の筆記試験に合格しても、総合技術監理部門の必須科目が合格しなければ、口頭試験に進めないので注意しましょう。
|
【技術士第二次試験に合格している場合は選択科目試験が免除になる】 技術士第二次試験の合格者が総合技術監理部門を受験する場合、 既に合格している技術部門・選択科目に対応する選択科目が免除になります。この場合は、総合技術監理部門の必須科目のみの受験で問題ありません。 |
2-3.【筆記試験合格者のみ】口頭試験
筆記試験に合格すると、口頭試験に進みます。
口頭試験では、技術士に関する経歴や役割認識など、技術士としての資質を確かめる質疑応答を行います。
技術部門と総合技術監理部門では評価項目が異なりますが、評価項目ごとに満点の60%以上を獲得できれば合格です。
|
部門 |
試験科目 |
|
技術士としての実務能力・技術士としての適格性 |
|
|
「総合技術監理部門」の必須科目に関する技術士として必要な専門知識や応用能力・技術士としての実務能力・技術士としての適格性 |
ここでは、口頭試験の試験内容や質問例をご紹介するので、口頭試験まで進んだ場合にどのような対策をすればいいのか把握しておきましょう。
2-3-1.技術部門の場合
技術部門の口頭試験では、試験官の質問に答えながら技術士としての適性を確認します。
具体的には20分(10分程度の延長あり)の間に「技術士としての実務能力」と「技術士としての適格性」を確認する質問をされるので、自分の言葉で解答します。
|
評価項目 |
合格基準 |
|
|
技術士としての実務能力 |
コミュニケーション、 |
60%以上 (30点満点) |
|
評価、マネジメント |
60%以上 (30点満点) |
|
|
技術士としての適格性 |
技術者倫理 |
60%以上 (20点満点) |
|
継続研さん |
60%以上 (20点満点) |
|
参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験 受験申込み案内」
技術士としての実務能力は今までの経験や実務経験証明書に記載した内容から、質問される傾向があります。
技術士としての適格性では、技術士法や技術士倫理綱領、業務に関する法令など、技術士として必要な資質について質問される傾向があります。
技術士に求められる役割や各専門分野の基礎知識も、分かりやすく改正できるようにしておきましょう。
|
【質問の例】 ・受験申込書に記載した「業務内容の詳細」について3分程度で説明してください。 |
2-3-2.監理部門の場合
総合技術監理部門の口頭試験は技術部門で尋ねられる質問項目に、「総合技術監理部門」の必須科目に関する質問が追加されます。
|
評価項目 |
合格基準 |
|
|
「総合技術監理部門」の必須科目に関する技術士として必要な専門知識や応用能力 |
経歴、応用能力 |
60%以上 (60点満点) |
|
体系的専門知識 |
60%以上 (40点満点) |
|
|
技術士としての実務能力 |
コミュニケーション・ |
60%以上 (30点満点) |
|
評価、マネジメント |
60%以上 (30点満点) |
|
|
技術士としての適格性 |
技術者倫理 |
60%以上 (20点満点) |
|
継続研さん |
60%以上 (20点満点) |
|
参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度技術士第二次試験 受験申込み案内 」
※前半20分、後半20分の時間割(10分程度の延長あり)
安全管理や人的資源管理など5つの管理に関する質問や、現場、企業を管理する立場に求められる応用力などを問う質問が多い傾向があります。
総合技術監理部門ならではの役割や特徴などを理解して、伝わられるようにしておく必要があるでしょう。
|
【質問の例】 ・携わっている業務について5つの管理の視点で解説してください。 |
3.技術士第二次試験の過去問を紹介

技術士第二次試験の概要が理解できたところで、実際にどのような問題が出題されるのか気になるところです。
ここでは、2024年度の技術士第二次試験の過去問を中心に、どのような問題が出題されるのかご紹介します。
|
過去問の科目 |
過去問の傾向 |
|
社会問題や現代社会の課題などをテーマに、技術士として課題を適切に捉え、具体的な解決策を示すことが求められる |
|
|
専門的な基礎知識を確認するための問題を中心に出題されている |
|
|
専門的な知識を踏まえて、技術士としての課題解決力や提案力などを確認する問題が出題されている |
|
|
企業や現場を管理するために必要な基礎知識がとわれる |
過去問はあくまでも一例なので、同じような問題が今後も出題されるとは限りませんが、問題の傾向やレベル感を確認してみてください。
3-1.技術部門の必須科目の過去問
まずは、技術部門の必須科目の過去問をいくつかご紹介します。
【2024年度の建設部門の過去問】
|
国が定める国土形成計画の基本理念として、人口減少や産業その他の社会経済構造の変化に的確に対応し、自立的に発展する地域社会、国際競争力の強化等による活力ある経済社会を実現する国土の形成が掲げられ、成熟社会型の計画として転換が図られている。 令和5年に定められた第三次国土形成計画では、拠点連結型国土の構築を図ることにより、重層的な圏域の形成を通じて、持続可能な形で機能や役割が発揮される国土構造の実現を目指すことが示された。 この実現のために、国土全体におけるシームレスな連結を強化して全国的なネットワークの形成を図ることに加え、新たな発想からの地域マネジメントの構築を通じて持続可能な生活圏の再構築を図る、という方向性が示されていることを踏まえ、持続可能で暮らしやすい地域社会を実現するための方策について、以下の問いに答えよ。 1.全国的なネットワークを形成するとともに地域・拠点間の連結及び地域内ネットワークの強化を目指す社会資本整備を進めるに当たり、投入できる人員や予算に限りがあることを前提に、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。 2.前問で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。 3.前問で示したすべての解決策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。 4.前問(1と3)を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。 |
【2024年度の上下水道部門の過去問】
|
我が国では, 水循環基本計画に基づき水循環に関する施策を着実に実施してきたところであるが、 健全な水循環の維持または回復にあたっては、依然として多くの課題が残されている。 今後の持続可能な社会の実現には、健全な水循環が不可欠であり、様々な分野での取り組みが求められている。 上記のような状況を踏まえ、 以下の問いに答えよ。 1.上下水道事業においても、健全な水循環構築のための取組が求められている。これについて、技術者としての立場で多面的な観点から、健全な水循環の構築に関して上下水道事業に共通する技術面の課題を3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。 2.前問で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げて、その課題に対する複数の解決策を, 上下水道の専門技術用語を交えて示せ。 3.前問で示したすべての解決策を実行したうえで生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項ヘの対応策を示せ。 4.1~4の業務遂行に当たり、技術者としての倫理, 社会の持続可能性の観点から必要となる要件・留意事項を題意に即して述べよ。 |
参考:公益社団法人日本技術士会「令和6年度技術士第二次試験問題(上下水道部門)」
このように、必須科目の過去問を見ると社会問題や現代社会の課題などをテーマに、技術士として課題を適切に捉え、具体的な解決策を示すことが求められています。
例えば、建設部門の問題では地域マネジメントにはどのような課題があり、技術士としてどのような解決策を提案できるのか問われています。
各部門の基礎知識、社会問題の把握はもちろんのこと、技術士の視点からどのような解決ができるのか問題解決能力や提案力が問われるでしょう。
3-2.技術部門の選択科目Ⅱの過去問
続いて、技術部門の選択科目Ⅱの過去問をいくつかご紹介します。
【2024年度建設部門 鋼構造及びコンクリートの過去問(Ⅱ-1)】
|
1.アーク溶接により鋼材を接合した際に生じる可能性のある溶接欠陥を2つ挙げ、それぞれの欠陥を説明し、その要因と留意点を述べよ。 2.軟鋼及び高張カ鋼について、引張試験から得られる応力-ひずみ曲線を機械的性質に関する用語と共に図示せよ。応力-ひずみ曲線は、6マス×15マス程度に図示すること。軟鋼と高張カ鋼の特性の違いを踏まえつつ、応力-ひずみ曲線から得られる機械的性質について3つ以上説明せよ。 3.コンクリート構造物の変状には、アルカリシリカ反応、塩害、火害などがある。この3種類の変状の中から1つ選択し、その変状のメカニズムを概説せよ。また選択した変状の程度を調査する方法、及び変状の程度を考慮した補修方法について述べよ。 4.コンクリート構造物の温度ひび割れの発生メカニズムについて説明せよ。また、温度ひび割れの抑制対策を2つ挙げ、それぞれについて目的と留意点を述べよ。 ※4つの設問から1つを選択して、解答を答案用紙1枚にまとめる問題です。 |
【2024年度機械部門 機械設計の過去問(Ⅱ-1)】
|
1.鍛造は、金属材料(ビレット)を圧縮若しくは打撃することで所望の形状を得る塑性加工法の1つである。鍛造部品を設計・成形加工するうえで設計者として考慮すべき事項を3つ挙げ、その理由を説明せよ。必要であれば図等を用いてもよい。 2.CAEを活用した設計を進める際に、解析の結果と実際の製品において性能に差が生じる場合がある。具体的な製品を示したうえで、CAEで誤差が生じる原因として考えられる入力条件を3つ挙げ、それぞれの理由を述べよ。 3.機械製品を設計するに当たり、安全設計思想を考慮することは重要である。その代表的な考え方であるフェールセーフとフォールトトレランスの各々について、その概要を述べ、思想が適用されている製品と実施内容を示せ。 4.具体的な機械製品(構造物・部品)を1つ取り挙げ、その製品の剛性を高める方法を3つ提案せよ。また一般的に高剛性化によって、強度上の損傷リスクが高まる場合も想定されるが、その理由を説明せよ。 ※4つの設問から1つを選択して、解答を答案用紙1枚にまとめる問題です。 |
参考:公益社団法人日本技術士会「令和6年度技術士第二次試験問題(機械部門)」
技術部門の選択科目Ⅱの過去問は、専門的な基礎知識を確認するための問題が中心です。
専門用語や計算方法、素材の性質など、選択した科目に関する深い理解が求められます。また、ただ専門的な知識を述べるのではなく理由や改善策、注意点などの説明を求めるケースもあり、得た知識を活用できるレベルまで理解しておく必要があるでしょう。
3-3.技術部門の選択科目Ⅲの過去問
技術部門の選択科目Ⅲの過去問をいくつかご紹介します。
【2024年度建設部門 施工計画、施工設備及び積算の過去問】
|
建設会社、建設コンサルタント、調査・測量会社等の建設関連企業は、自然災害が発生した直後からインフラ施設の管理者である国、自治体、民間企業等からの要請、指示、委託等を受け、インフラ機能の早期回復や被災影響の低減を図るうえで必要不可欠な役割を果たしている。 今後気候変動による災害の激甚化・頻発化が懸念されるなかで効果的に災害応急対策を実施するには、被災状況に応じて、利用可能な資源を適切に割り当てる等の調整・マネジメントを実施したうえで、適切な契約を行うことが極めて重要である。 このような状況を踏まえ、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者としての経験と知見に基づき、以下の問いに答えよ。 1.災害応急対策を実施するため、インフラ施設の管理者と建設関連企業が契約を締結するに当たり、投入できる人員や予算に限りがあることを前提に、多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで,その課題の内容を具体的に示せ。 2.前問で示した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を専門技術用語を交えて示せ。 3.前問で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。 |
【2024年度電気電子部門 情報通信の過去問】
|
DX化や機器の進化により情報通信ネットワークサービスを提供するために必要なライフサイクルマネジメントやサプライチェーンマネジメントは、より複雑化している。 大手企業であっても従来のように、上流から下流まですべてを自社の仕様や製品のみでは実現できない。 情報通信機器は近年海外で製造される機器に依存しつつある。また、安心・安全な企業活動のために、物理的に離れた設備拠点の設置や機器のバージョン管理も重要となる。 このように複雑化した環境下で情報通信ネットワークサービスを提供するためには、セキュリティやその対策を考えるだけでなく、総合的な情報通信ネットワークの管理・運用を考える必要がある。 例えば単に予備機器のストックやセキュリティの対策をしておくことだけでなく、情報通信にとどまらず関連する幅広い技術領域の変化やその影響度,社会情勢,将来予測などを総合したハードウェア・ソフトウェア両面を含めたレジリエントな情報通信ネットワークの管理・運用体制の構築が鍵である。 1.上記を踏まえ、安定した情報通信ネットワークサービス提供を実現する際の具体的な検討項目について、多面的に異なる観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を説明せよ。 2.前問で抽出した技術課題のうち最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、これを最も重要とした理由を述べよ。その技術課題に対する情報通信分野関連における解決策を3つ、技術的にできるだけ深掘りして情報通信分野の専門技術用語を交えて示せ。 3.前問で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。 |
参考:公益社団法人日本技術士会「令和6年度技術士第二次試験問題(電気電子部門)」
技術部門の選択科目Ⅲの過去問は専門的な知識を踏まえて、技術士としての課題解決能力や提案力などを確認する問題が中心です。
選択科目Ⅱとは異なり社会問題や専門分野に関する課題などの問題を読んだ後に、具体的な課題や解決策などの提示が求められます。
問題形式としては必須科目と似ていますが、より専門的な知識を踏まえて記述する必要があるでしょう。
3-4.総合技術監理部門の必須科目の過去問
ここでは、総合技術監理部門の2024年度の択一式の過去問の一部をご紹介します。
【2024年度総合技術監理部門の択一式の過去問】
|
いわゆる労災保険(労働者災害補償保険)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1.労災保険制度は、労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い併せて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度である。 2.労災保険における労働者とは職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいい、アルバイトやパートタイマー等も含まれる。 3.労働者以外の中小事業主、一人親方、自営業者は,労災保険に加入することはできない。 4.複数の事業場で働いている労働者に関する労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額が決定される。 |
|
米国国立標準技術研究所(NIST)が発行した「NISTによるクラウドコンピューティングの定義」に示されている、クラウドコンビューティングの実装モデルに依存しない基本的な特徴を表す記述として、次のうち最も不適切なものはどれか。 1.オンデマンド・セルフサービスである。 |
参考:公益社団法人日本技術士会「令和6年度技術士第二次試験問題(総合技術監理部門)」
総合技術監理部門の択一式では、企業や現場を管理するために必要な基礎知識が問われます。
労働環境に関する法律やキャッシュフロー管理、設備管理など幅広い知識が求められるでしょう。
記述式では技術部門の必須科目のように文章を読み、具体的な改善策や課題などをまとめます。
4.技術士第二次試験の平均勉強時間は約500~800時間

技術士第二次試験の平均勉強時間は、約500~800時間です(口頭試験を除く)。
 既に持ち合わせている知識量にもよりますが、第一次試験と比較すると2~4倍程度の勉強量が必要になります。
既に持ち合わせている知識量にもよりますが、第一次試験と比較すると2~4倍程度の勉強量が必要になります。
第二次試験の勉強は、試験3ヶ月~6ヶ月前に開始するケースが多いです。半年前から勉強を開始すると、毎日約2.7時間~4.4時間勉強をして試験に望むことになります。
「技術士第二次試験の平均合格率は16.8%(2023年度時点)」でもお伝えしたように、第二次試験に合格するには平均4回受験すると言われています(建設部門・筆記試験の場合)。
なかなか受からないと毎年この勉強量を続けなければならないので、技術士第二次試験に合う正しい勉強方法で効率よく合格を目指すことが重要でしょう。
5.技術士第二次試験に受かった人の声

技術士第二次試験の具体的な試験内容が分かったところで「どのように技術士第二次試験に合格できるのか」リアルな声が気になるところです。
ここでは「技術士の学校」に通い第二次試験に合格した先輩の挫折や勉強方法、合格後の思いなどをまとめてご紹介します。
先輩はどのように第二次試験に挑んだのか、リアルな声を参考にしてみましょう。
|
第二次試験合格者 |
合格までの過程 |
|
・独学では得意分野の問題でも全て成績B評価で不合格だった ・テクニックと知識、文章力の3つをしっかりと学び第二次試験に合格 |
|
|
・独学で9回受験して不合格だった ・効率のいい勉強法とオンライン環境で知識をつけて第二次試験に合格 |
|
|
・数年間独学で勉強したが2回不合格が続いた ・オンライン上の仲間と切磋琢磨しながら勉強して第二次試験に合格 |
5-1.独学で挫折をして筆記試験にはテクニックが必要だと実感した
|
羽場内玲さん(受験部門:都市及び地方計画) |
|
|
第二次試験の所感 |
・独学では得意分野の問題でも全て成績B評価で不合格だった ・漠然と勉強していても何も変わらないと感じた |
|
第二次試験の取り組み方 |
・技術士の学校でテクニックと知識、文章力の3つを学んだ ・リアルタイムで講義を受けるようにスケジュール管理をした ・過去問を使い答案例をたくさん作成した |
|
試験合格後の声 |
・社内での評価が上がりプロジェクトに呼ばれることが増えた ・顧客と専門用語を交えて話せるようになった |
コンサルタント会社で働く羽場内 玲さんは、独学での第二次試験に悪戦苦闘していました。得意分野の問題でも、全て成績B評価で不合格。
理解していると思っていた分野でも、思ったような評価が得られず、ただ漠然と勉強していても何も変わらないと感じたそうです。
何年も受験をすることは避けたかったので、会社の資格補助制度を活用して「技術士の学校」を利用。
テクニックと知識、文章力の3つを教えてもらえる場所として、役に立ったとのこと。
とくに、リアルタイムで受講できる講座は集中力が持続し、講師の話を直接聞けるところに魅力を感じたそうです。
適切なサポートを受けながら必要な勉強に取り組めたことで、第二次試験に合格できました。合格後は社内での評価が上がり、プロジェクトに呼ばれることが増えました。
顧客と専門用語を交えて話せるようになり、合格してよかったと感じているとのことです。
▼羽場内 玲さんの事例は下記で詳しく紹介しています。
技術士試験は近道がない試験ではあるが、基本に忠実にしっかり勉強すれば合格できる試験だとわかった
5-2.独学では難しい試験だと痛感!正しい学び方で合格できた
|
安藤圭吾さん(受験部門:建設環境部門) |
|
|
第二次試験の所感 |
・独学で9回受験して不合格だった |
|
第二次試験の取り組み方 |
・技術士の学校で効率よく必要な知識を習得した ・海外出張が多いがオンライン講義なので場所や時間問わず勉強できた |
|
試験合格後の声 |
・真価はこれから問われるものなので自己研鑽を続けたい ・いずれは総合技術監理部門に挑戦したい |
コンサルタント会社で勤務する安藤圭吾さんは、独学で9回受験して不合格だったそうです。そこでしっかりと筆記試験対策をしようと思い「技術士の学校」を利用することにしました。
講座を受講すると今までの勉強がいかに非効率であったか実感したそうです。資料などの説明が丁寧で、分からないことは質問ができるので講座のスピードにもついていくことができました。
海外出張が多く講義を受けられるか不安があったものの、オンラインだからこそ地域問わず学習を進められたとのことです。
見事技術士第二次試験に合格し、技術士としての出発点に立ちました。
真価はこれから問われるものなので自己研鑽を続け、後には「総合技術監理部門」にも挑戦したいと考えています。
▼安藤圭吾さんの事例は下記で詳しく紹介しています。
自分が行ってきた勉強法が如何に非効率だったかをまざまざと実感させられた
5-3.クラスの仲間と切磋琢磨しながら合格できた
|
須田暁憲さん(受験部門:都市及び地方計画) |
|
|
第二次試験の所感 |
・数年は独学で漠然と白書を読む、過去問を解くなどの勉強をしていましたが、2回ほど不合格が続いた |
|
第二次試験の取り組み方 |
・事前課題や準備に苦戦したがその中で力がついた ・オンライン上の仲間と切磋琢磨しながら勉強できた ・クラス中での事前課題への指摘が一つ一つ身になった |
|
試験合格後の声 |
・試験勉強を通じて技術が身についた ・合格後の業務や周囲の方の反応を通して技術士の信頼度の高さを実感した |
須田暁憲さんは、建設コンサルタントとして働く中で技術士資格の必要性を感じていました。数年は独学で漠然と白書を読む、過去問を解くなどの勉強をしていましたが、2回ほど不合格が続いたそうです。
そこで独学での勉強に限界を感じて、技術士の学校を利用しました。
受講してしばらくの間は事前課題や準備に苦戦しましたが、その中で力がついてきていると感じたそうです。ただ事前課題や資料を覚えるのではなく、自分なりに理解していくことも意識して取り組みました。
また、講義の中では演習があり解答を他の受講生とチャットで共有するので、オンライン上の仲間と切磋琢磨しながら勉強できたとも感じたそうです。勉強をしても不合格になってしまったときには、講師からの「実力はあるので、あとは諦めずに受け続けることが大事」という言葉が支えになりました。
無事に第二次試験に合格でき、試験勉強を通じて技術が身についたと感じています。合格後の業務や周囲の方の反応を通して「技術士」の信頼度の高さを実感できました。
▼須田暁憲さんの事例は下記で詳しく紹介しています。
正しい試験対策が技術研鑽になり、名実ともに「技術士」になることができた
6.技術士第二次試験の勉強方法

技術士第二次試験に合格した先輩たちの声を聞き「試験勉強が難しそう」と感じた方もいるでしょう。
技術士第二次試験は独学での勉強が難しい試験なので、学校や講座などに通い知識を身につけます。学校や講座に通いつつ、自主勉強をするときには、下記の3つがポイントになります。
この3つは技術士第二次試験の勉強を始める前に知っておきたいポイントなので、チェックしておきましょう。
▼技術士試験の勉強方法は下記の記事でより詳しく解説しています。
「技術士 勉強方法」
6-1.第二次試験の合格者からアドバイスをもらう
第二次試験の勉強をするときにぜひ実践して欲しいのが、第二次試験の合格者からアドバイスをもらうことです。
一人で黙々と答案を作成しても、この「内容で合っているのか」「この書き方が適しているのか」判断することが難しいです。そこで、既に第二次試験に合格している先輩や友人に添削、アドバイスを依頼すると、実体験をもとに的確な指摘をしてもらえます。
|
【合格者に依頼したいアドバイスの内容例】 ・作成した答案の添削 |
とくに、社内に技術士試験合格者が多い環境ではノウハウが蓄積されているため、積極的にアドバイスを求めるといいでしょう。
|
【社内に技術士第二次試験支援制度がある場合は活用する】 会社によっては技術士資格取得を支援するために、勉強のサポート体制や資格取得費用の補助などを用意しているケースがあります。 |
6-2.過去問を分析して出題傾向の多いキーワード、資料などを理解する
第二次試験の筆記試験では、過去問を分析して出題傾向の多いキーワード、資料などを理解することが大切です。第二次試験は範囲が広く闇雲に勉強しても、なかなか知識が蓄積されていきません。
そこで、過去問の傾向を掴み、どのようなキーワードや白書、資料などを理解するべきか検討しましょう。
一例として、建設部門(必須科目)では、下記のテーマを出題する傾向があります。
|
【建設部門の出題傾向の多いテーマ】 ・建設分野の発展(生産性向上・担い手確保など) |
このテーマに紐づくキーワードを白書、資料などを整理して理解すると、正しい知識をもとに答案作成ができるでしょう。
▼建設部門(必須科目)の重要キーワードの見つけ方は、下記の記事で解説しています。
技術士筆記試験対策(建設部門)Ⅰ必須科目 重要キーワード
6-3.できるだけ多くの過去問を解く
第二次試験の筆記試験に必要な知識が身についてきたら、できるだけ多くの過去問を解いて問題や解答形式に慣れることが必要です。このときに闇雲に過去問を解くのではなく、下記のステップを意識してみましょう。
|
第二次試験(筆記)の過去問に取り組むステップ |
|
|
ステップ1 合格ラインの答案を1つずつ丁寧に |
時間がかかってもいいので、合格ラインとなる答案を丁寧に作成してコツを掴む |
|
ステップ2 10問程度の過去問にチャレンジする |
10問程度の過去問に取り組み、答案と問題点、解決策をセットにして記載する |
|
ステップ3 過去6年分の様々な問題を解く |
過去6年分の構成と見出しをたくさん制作して、様々な問題に慣れる |
まずは、合格ラインの答案を丁寧に作成して、合格となる答案作成のコツを掴みます。合格ラインの答案が一定数できたら10問程度の過去問に取り組み、答案と問題点、課題をセットにまとめましょう。
ここまで来たら過去6年分の様々な過去問を解き、どのようなテーマが出題されても対応できるように練習します。
過去問を解く中で分からないことがあったら、修正後に参考書や白書、自作のキーワード集などを見て、どの問題にどの知識が必要なのか紐づけると、同じミスをしにくくなるでしょう。
▼過去問は下記で公開されているので、活用してみてください。
公益社団法人日本技術士会「過去問題(二次試験)」
7.技術士第二次試験は答案作成のテクニックも求められる

第二次試験は記述式なので、答案作成のテクニックも求められます。
第一次試験は択一式なので正しい知識があれば解答できますが、記述式は知識だけを詰め込んでも解答できません。
|
試験 |
解答方法 |
ポイント |
|
第一次試験 |
択一式 |
・複数の選択肢から正解を1つ選ぶ ・正しい知識を持っていれば解答できる |
|
第二次試験 |
記述式 口頭式 (総合技術監理部門の一部を除く) |
・正解が1つではないので自分のケースに当てはめて最適な記述をしなければならない ・正しい知識があっても論文を書く力や問題解決能力がなければ合格できない |
例えば、下記の問題があったときに、鍛造の定義を理解しているだけでは解答できません。
設計者の立場から考慮するべき点を見極め、正当な理由を論理的に述べる必要があります。
|
【第二次試験の問題例】 鍛造は、金属材料(ビレット)を圧縮若しくは打撃することで所望の形状を得る塑性加工法の1つである。 |
第二次試験に挑んでも合格できない原因で多いのは、論文を書くための知識習得を怠ったケースです。もちろん、第二次試験を解くための知識は必要ですが、それと同時に論文の構成作成方法や考え方、文章力なども身につける必要があるでしょう。
8.難易度の高い答案作成力を身につけるために「技術士の学校」で対策しませんか

※技術士第二次試験(筆記)の建設部門に対応
ここまで、技術士第二次試験の概要や試験内容、勉強方法などをまとめて解説してきました。
第二次試験は第一次試験とは大きく異なり、確かに合格率が低く難易度が高い試験です。しかし、合格に至らなかった方の声を見てみると「勉強するべきポイントが違っていた」「闇雲に過去問ばかりを解いていた」など、第二次試験に合う勉強方法ができていなかったケースが非常に多いです。
つまり、第二次試験合格を目指すと決めた段階から正しい勉強方法で取り組めば、効率よく合格を目指すことができるのです。
技術士第二次試験(建設部門)に特化したオンラインスクール「技術士の学校」では、合格に必要な勉強方法からしっかりと学び「早く」「効率よく」合格を目指せます。実際に「技術士の学校」の合格率は49%、平均2.1年で合格ができています。

※技術士の建設部門 第二次試験(筆記試験)の場合
※実践コースを受講して適切に修了した受講者等の割合
通常よりも約5倍の合格率で約2年早く合格を目指すことで、いち早く技術士として活躍できます。ここでは、私たち「技術士の学校」の特徴をご紹介するので、これから第二次試験に挑戦する方や第二次試験勉強に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。
8-1.合格に必要な本当の勉強方法を学べる
技術士第二次試験の筆記試験は、正しい勉強法を知らないと合格が難しい試験です。とは言え、技術士第二次試験は、正しい勉強方法のノウハウが出回っていない傾向があります。
私たち「技術士の学校」は15年以上にわたり技術士試験の支援をしてきた経験から、本当の勉強方法を知ることが非常に重要だと考えています。
そのため、基本コースでは、本当の勉強方法の理解を目的としたカリキュラムを設定しています。
|
【基本コースのカリキュラムの一例】 ・試験のルールを理解する |
第二次試験ならではのルールや勉強方法、論文の構成作成方法などの基礎から学ぶため、第二次試験に合格するための土台を固められます。
本当の勉強方法を理解したうえで各科目の勉強をすることで、合格までの最短ルートを辿り必要な知識、技術を効率とく習得できます。
8-2.考え抜かれたカリキュラムで勉強時間を短縮
「技術士の学校」では、大手建設コンサルタント会社で建設部門に従事した講師陣が、建設部門に特化したカリキュラムを作成しています。
|
【カリキュラムの特徴】 ・20年以上技術士試験に携わってきた講師陣がカリキュラムを作成 |
独学では難しい採点マニュアルを踏まえた答案の書き方や、出題傾向を踏まえたキーワード分析など、効率よく合格するためのカリキュラムが揃っています。また、多くの受講生データに基づく根拠のあるアドバイスも実施しており、合格するためのフォロー体制にも力を入れています。
8-3.忙しい人でも継続しやすいオンライン型の受講形式
第二次試験の勉強を始めるときに、仕事やプライベートと両立できるのか不安になる方も多いかと思います。「技術士の学校」はオンラインスクールで、「ライブ型」と「動画視聴型」の2つの受講形式を用意しています。
住まいの地域や働き方などに囚われることなく、どこからでも講義を受講できます。

また、講師や仲間と交流できるため、切磋琢磨しながら第二次試験の合格を目指せる点もポイントです。「技術士の学校」の受講生からは「独学では合格できなかったけれど、勉強方法が分かり短期間で合格できた」「丁寧で分かりやすい講義で理解しやすかった」などの声をいただいています。

技術士の第二次試験は技術士を目指すうえでの関門と言われており、独学では理解しきれないポイントが多々あります。
9.まとめ
この記事では、技術士第二次試験の概要や試験内容、勉強方法など、第二次試験を受験する前に知っておきたい情報をまとめてご紹介しました。
最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。
〇技術士第二次試験の受験条件は下記のとおり
ケース1:修習技術者で技術士補として通算4~7年以上の実務経験がある
ケース2:修習技術者で職務上の監督の下で通算4~7年以上の実務経験がある
ケース3:修習技術者で技術資格に関する実務経験が7~10年以上ある
〇技術士試験の合格基準は、指定範囲ごとに全得点の60%以上の得点を取得すること
〇技術士第二次試験の平均合格率は16.8%(1958年~2023年度までの平均)
〇技術士第二次試験の流れが下記のとおり
ステップ1:第二次試験の申し込みに必要な書類・費用を揃える
ステップ2:期日内に申し込みをする
ステップ3:筆記試験を受ける
ステップ4:筆記試験合格者のみ口頭試験を受ける
ステップ5:技術士の登録をする
〇技術士第二次試験(技術部門)の筆記試験内容は下記のとおり
|
科目 |
概要 |
|
必須科目Ⅰ |
記述式 技術部門ごとの基礎知識を使い問題解決方法を提示する |
|
選択科目Ⅱ |
記述式 専門科目の基礎知識と応用力を確認する |
|
選択科目Ⅲ |
記述式 専門科目の問題解決能力、課題遂行能力を確認する |
〇総合技術監理部門の筆記試験内容は下記のとおり
|
科目 |
概要 |
|
必須科目 |
択一式 総合技術監理に必要な基礎知識を確認する |
|
記述式 最新のテーマを踏まえながら総合技術監理に必要な応用力を確認する |
|
|
選択科目Ⅰ |
記述式 技術部門ごとの基礎知識を使い問題解決方法を提示する |
|
選択科目Ⅱ |
記述式 専門科目の基礎知識と応用力を確認する |
|
選択科目Ⅲ |
記述式 専門科目の問題解決能力、課題遂行能力を確認する |
〇筆記試験に合格すると口頭試験に進める
〇技術士第二次試験の平均勉強時間は500~800時間(筆記試験のみ)
〇技術士第二次試験の勉強のコツは下記の3つ
1.第二次試験の合格者からアドバイスをもらう
2.過去問を分析して出題傾向の多いキーワード、資料などを理解する
3.できるだけ多くの過去問を解く
技術士第二次試験は合格率が低く難易度が高い試験ではあるものの、正しい勉強方法が分かれば効率よく合格に近づけます。技術士第二次試験の勉強方法に課題やお悩みがある場合は「技術士の学校」の無料体験を受けて、本当の勉強方法を体感してみてください。
筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。さらに、受験者から採点方法がみえにくいため、対策・改善の方向性等がわかりにくい試験です。対策・改善の方向性等がわからなければ、何度受験しても不合格になってしまいます。
一方、「建設部門」では、技術士の学校の合格率は46%(女性の合格率73%)(令和元年度〜令和6年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。 勉強の方法がわからない方、早く合格したい方、試験にあまり時間をかけたくない方等は、技術士の学校の筆記試験対策講座を受講してみるのはいかがでしょうか。
講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。
技術士の学校の合格実績(建設部門)
【令和元年度〜令和6年度 筆記試験合格実績】
(建設部門)
通常の合格率10%程度
合格率 46%
女性の合格率 73%
※実践コース受講者等
合格者 153人
女性の合格者 33人
合格率が通常の5倍!2年早く技術士を取得!
技術士試験は、厳格な国家試験で、筆記試験は合格率10%程度の非常に難しい試験です。
このため、5回以上受験しても合格できないこともざらにあり、途中で諦める方も少なくないのが現実です。
累積すると、毎年の勉強時間だけでなく、受験手数料もそれなりの負担になります。
「技術士の学校」の筆記試験対策講座では、筆記試験の正しい勉強方法に加え、必須科目を中心に重要キーワードの体系的な理解を深めることで、最短ルートの合格を提供します。
「技術士の学校」なら通常よりも合格率が5倍、2年早く技術士を取得し、貴重な時間を無駄にしません。
全国どこからでも受講可能なオンライン講座(リアルタイム形式)です。
カリキュラム開発(建設部門)
下所 諭 (げしょ さとし)
技術士(建設部門、総合技術監理部門)
大手建設コンサルタント会社で13年間勤務。広島大学 客員准教授 (2017~2024年)。
大手建設コンサルタント会社在籍時から含めて、10年以上、技術士の取得支援に携わっています。知見が集積する大手建設コンサルタント会社等でないと合格が難しいですが、多くの受講生を技術士の取得に導いています。
成績90%の高得点答案データを分析!

※答案は受講生が筆記試験後に再現したもので、点数は公益社団法人日本技術士会に問い合わせて確認したものです。
キーワードの記述例(サンプル)

※キーワードの記述例はⅠ必須科目(建設部門)における重要な4テーマについて、それぞれ10個以上、計50個以上を整理。
<クラス内容の一例>合格の最短ルート!筆記試験のキーワード学習動画(サンプル)
実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。
<クラス内容の一例>筆記試験80%近い高得点の答案の例!高得点再現答案集(サンプル)
実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。
<クラス内容の一例>建設部門I必須科目 重要テーマ
実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。
<クラス内容の一例>一瞬でわかる!合格する論文構成の考え方
実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。
合格者インタビュー
羽場内 玲さん 都市及び地方計画 コンサルタント会社 東京都在住
髙野 健人さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント 大分県在住
合格者インタビュー(建設部門)

澁谷満博さん 施工計画、施工設備及び積算 奥村組土木興業株式会社 大阪府在住
半年前には手の届くはずのない資格であったはずが、諦めなければ必ず取得できる資格になったと感じた。
澁谷満博さん 施工計画、施工設備及び積算 奥村組土木興業株式会社 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 現場監督として従事していた私には技術士は…

清水里美さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント 宮城県在住
効率的に勉強して、早く合格したかった。自分にプレッシャーをかけて力に変えた。
清水里美さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 効率的に勉強して、早期に合格したかったです。 建設コン…

平田周作さん 施工計画、施工設備及び積算 大手ゼネコン 岡山県在住
実際に自分の目で、真剣に試験勉強している受験生を見ることがモチベーションに繋がった。
平田周作さん 施工計画、施工設備及び積算 大手ゼネコン Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 何度も不合格になり、これまでの自身の勉強方法が良く…

當山真由美さん 都市及び地方計画 合同会社ユーエスディラボ 沖縄県在住
地方では情報を入手しにくかった。実務経験だけでは知り得ることができない幅広い技術を学ぶことができた。
當山真由美さん 都市及び地方計画 合同会社ユーエスディラボ Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 特に地方では試験に関する情報が少なく、独学での…

久松貞之さん 道路 株式会社アサヒコンサルタンツ 茨城県在住
論文構成やキーワード記述例も学習できるため、答案の書き方が分からない人は講座の受講が有効と思った。
久松貞之さん 道路 株式会社アサヒコンサルタンツ Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 技術士を取得して、専門家としての信頼性を高め、業務の質を…

加藤慶太朗さん 鋼構造及びコンクリート 製造業インフラ関連部署 愛知県在住
製造業に所属する私でも建設部門の技術士を取得できた。建設業で専門的な仕事をしている方は真剣に受験すれば合格できると感じた。
加藤慶太朗さん 鋼構造及びコンクリート 製造業インフラ関連部署 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 専門分野を明確に持ちたいと思い、技術士を取…

大西絢子さん 建設環境 株式会社竹中土木 東京都在
仕事、家事、育児と山盛りの毎日を過ごす中で、1分1秒も無駄にできない。
大西絢子さん 建設環境 株式会社竹中土木 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 仕事、家事、育児と山盛りの毎日を過ごす中で、1分1秒も無駄にでき…
\合格率5倍の講座を無料体験/
関連コラム
技術士第二次試験 試験で確認される能力(総合技術監理部門を除く技術部門)
技術士(建設部門)筆記試験 一発合格は可能か? 社外セミナーを受講すべきか?
技術士第二次試験合格体験記 建設部門 建設コンサルタント会社勤務Aさん 受験動機を成長させる